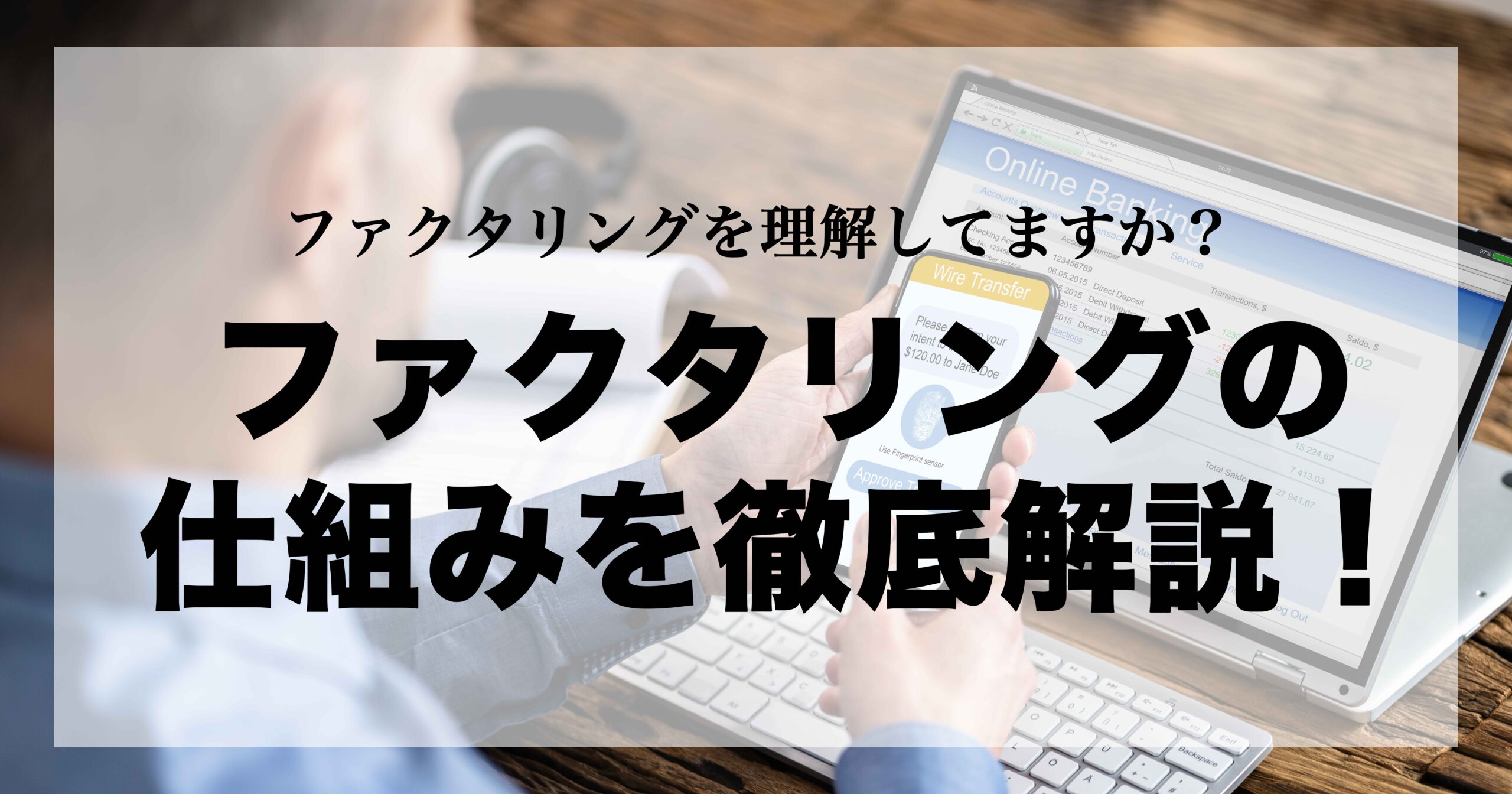資金繰りに悩む中小企業や個人事業主にとって、ファクタリングは有力な資金調達手段として注目されています。
特に近年では「クラウドファクタリング」という新しいサービスも登場し、「従来のファクタリングと何が違うのか?」と疑問に思う方も増えています。
本記事では、ファクタリングとクラウドファクタリングの違いについてわかりやすく解説します。
なぜこの質問が多いのか
資金繰りが厳しい状況では、銀行融資以外の方法に目を向ける経営者が多くなります。その中でファクタリングは「売掛金をすぐ現金化できる」仕組みとして魅力的ですが、最近ではオンラインで完結するクラウドファクタリングも登場し、どちらを選べばいいか悩む方が増えています。
また、仕組みや手数料の違いが見えにくいため、誤解やトラブルの元にもなりがちです。
ファクタリングとクラウドファクタリングの違い【結論】
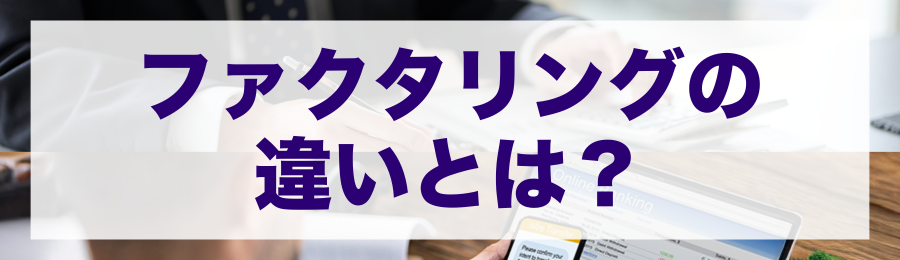
即日ファクタリングとクラウドファクタリングの主な違いは「手続きの方法」と「提供される仕組み」です。
従来型のファクタリングは対面や書面での手続きが主流であるのに対し、クラウドファクタリングはオンライン上で完結するサービスです。
仕組みそのものは類似しており、どちらも売掛債権(請求書)を資金化する点では同じです。
ファクタリングとは?その基本と仕組み
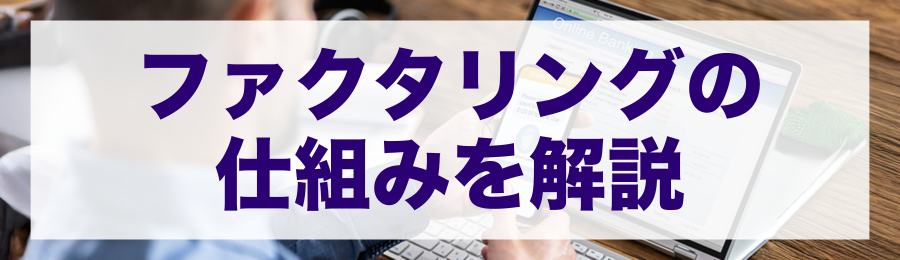
ファクタリングとは、企業が保有する売掛金(未回収の請求書)をファクタリング会社に売却し、早期に現金化する仕組みです。
2社間ファクタリング(債務者に通知しない)と3社間ファクタリング(債務者に通知する)の2種類があります。
この仕組みにより、企業は売掛先からの入金を待たずに、資金を調達することができます。 主に中小企業やベンチャー企業が、資金繰りの安定や急な支払いへの対応に活用しています。
クラウドファクタリングとは?デジタル時代の新しい資金調達
クラウドファクタリングは、ファクタリングの手続きをオンライン上で完結できる新しいサービス形態です。
書類提出や本人確認、契約手続きなどを全てWeb上で行えるのが特徴です。
よくある誤解と注意点
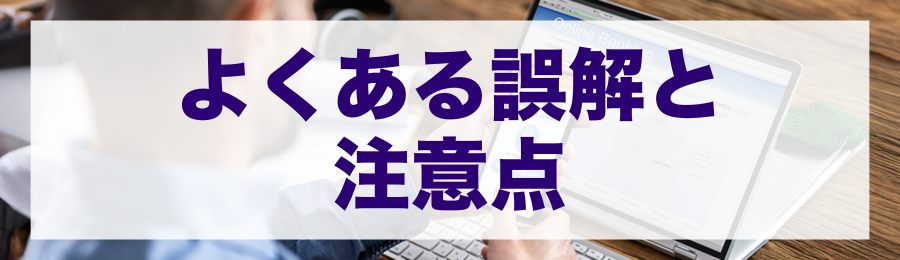
「クラウドファクタリングは手数料が安い」「審査が緩い」という誤解がありますが、必ずしもそうとは限りません。
手数料は売掛先の信用力や請求金額、サービス提供会社によって異なりますし、クラウド化されていてもリスク審査はしっかり行われます。
また、クラウドファクタリング=すべて自動化・AI判断というイメージを持つ方もいますが、実際には担当者による審査が入る場合も多くあります。
実務での注意点
ファクタリングを利用する際は、「売掛先との契約内容」「請求書の信頼性」「債権譲渡通知の有無」など、細かい点でトラブルになることがあります。
特に2社間ファクタリングでは、売掛先に通知されないため、信用問題に発展するリスクがあります。
クラウドファクタリングでも、契約の電子署名の正当性やセキュリティ対策をしっかり確認することが大切です。
また、資金調達スピードばかりを重視せず、手数料や契約条件を慎重に比較しましょう。
専門家による支援が有効なケースとは
行政書士や中小企業診断士などの専門家は、即日ファクタリング契約書のチェックや、資金繰りの全体戦略のアドバイスを提供できます。 また、事業計画や財務内容を見直すことで、ファクタリングに頼らない健全な経営体制を築く支援も行えます。
特にクラウドファクタリングを初めて利用する場合は、どのサービスを選ぶべきか、契約の法的リスクはないかなどの相談が有効です。
まとめ:目的と状況に応じた使い分けを
ファクタリングとクラウドファクタリングは、どちらも「売掛金の早期現金化」という目的は共通していますが、利用方法や利便性に違いがあります。
オンライン完結の利便性を重視するならクラウドファクタリング、信用性や実績のある対応を求めるなら従来型も選択肢となります。
どちらを選ぶにしても、契約内容やリスクを十分に理解し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。